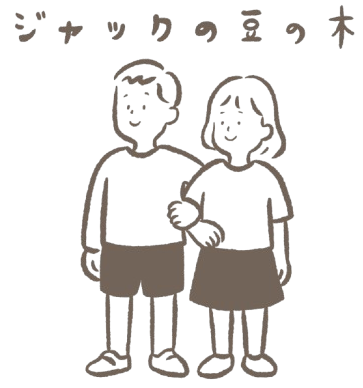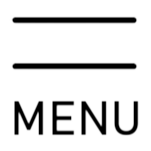FAQ
よくあるご質問
0〜18歳で、保育園や幼稚園、小・中・高校(特別支援学校含む)などに通い、集団生活に適応が難しいお子さん。障害の有無にかかわらず、困りごとがあれば利用対象になります(診断や手帳がなくても可能です)
市区町村の窓口または障害児相談支援事業所を通じて「受給者証」を取得し、面談にてアセスメントをしっかりさせて頂き訪問支援事業所と利用契約を結びます 。
意向の整理:今後どういう方向で関わってほしいか、目標や希望を明確にしていきます。
保育園、幼稚園、認定こども園、小学校〜高校、乳児院、児童養護施設などがおもな訪問先です。支援は児童指導員・保育士・作業療法士・心理士などが担当し、現場での直接支援や職員への助言を実施させて頂きます。
利用には「受給者証」必須です。通常、自己負担は利用料の1割で、所得に応じて月額負担上限があります(非課税世帯:0円、~年収890万円:4,600円、超:最大37,200円程度) 。また、3〜5歳児の無償化・幼児教育・保育無償化などで費用がかからないケースもあります 。
まずは、「保育所等訪問支援」という制度を利用したいとお考えであることを、担任の先生や園・学校の担当の先生にお伝えください。
たとえば、「子どものことで、保育所等訪問支援の利用を考えています。園(または学校)に訪問していただく形になりますが、ご相談させていただけますか?」といった形でお話しいただくとスムーズです。
支援の内容や訪問の流れについては、こちらから園・学校側に改めてご説明いたしますので、ご安心ください。
保護者の方が現場に同席する必要は基本的にありません
支援が終わったその日のうちに連絡帳にてお伝えさせて頂きます。支援記録、報告書作成、訪問記録や保護者・園への報告が必須になります。ご心配な事があればご連絡下さい。
支援員は、目立たない形で環境調整や声かけの工夫を提案し、全体の安心感・居心地を高める支援を行います
他児童とも話をしたりコミニュケーションをとっていきます。
クラス全体のバランスを崩さない配慮が取り入れられます 。
前もって同行し顔合わせをさせて頂きます。
ジャックの豆の木の訪問支援は
計画を作成する児童発達支援管理責任者と複数の訪問支援員がチームで対応する仕組みになっています。
そうすることで多角的な視点からのアセスメント
複数の専門職(相談支援専門員、児童指導員、保育士、心理士、OT/PTなど)が集まることで、一人では気づきにくい課題や視点に気づくことができます。
そのため、訪問支援員が変わる場合もありますが、児発管が責任を持って計画を継続・管理し、情報共有や引き継ぎもきちんと行われます。保護者さまへもきちんとご説明させて頂きます。
はい、利用予定のキャンセルや変更は可能です。
事業所の「重要事項説明書」や契約書には、「当日の朝までに連絡すればキャンセル可」という記載例が一般的です 。朝8時~9時迄にご連絡頂ければキャンセル料はかかりません。
ご安心ください。支援は対象のお子さんに向けて実施され、ご兄弟への影響については十分に配慮されます。兄弟児が同じ園にいても、支援中は対象児に集中し、兄弟が気にならないよう配慮されます。
兄弟への影響は殆どありません。
また、訪問支援による支援体制は、園や学校への活動を妨げないように環境や時間帯に配慮して実施されます。
加配(加配支援員)は、園や学校が配置する職員で、日々の保育や授業の中でお子さまと継続的に関わる支援者です。園・学校に常勤しているため、日常的な生活や活動を身近でサポートします。
一方、保育所等訪問支援は、外部の事業所から専門職(例:臨床心理士、公認心理師、児童指導員など)が訪問し、
• お子さまの様子を観察しながら支援する
• 環境調整や関わり方について先生方と相談する
• 必要に応じて保護者とも連携する
といった、第三者的な立場からの支援を行うのが保育所等訪問支援員です。
どちらもお子さまの安心と成長を支えるための支援ですが、役割や関わり方には違いがあります。状況に応じて、加配と訪問支援が連携して関わることも可能です。
ひとりで悩まず、どうか私たちにお話をお聞かせください。
代表取締役
児童発達管理責任者
石田智佳子